思春期からの友人のおばあさまは日本橋区人形町の間口の広い家に住んでいたが関東大震災で被災し関西に疎開した。
関西は地震が少ないことに驚いた一家は神戸に移住した。
絵の上手な上品なおばあさまだった。
が、阪神淡路大震災があり、タンスが倒れてきたがベッドの柵があったおかげで押し潰されずに済んだ。
義母は関東大震災の数日前に浅草で生まれ、首が座る前におぶわれて避難した。
本所の被災者住宅で育つ中で震災の恐ろしい話をたくさん聞いて地震に対してはとても神経質だったと夫談。
東日本大震災の時は寝たきりだったのに飛び起きて金属が入った足で息子たちがいた部屋まで移動してきた。
今の家は義父の死後に建て替えたが、義母が地震を怖がり柱がとても多いつくりになっている。
なお以前の屋敷は深い穴を掘りそこに石を積み、大きな石の上に柱を設置し、その柱の中には鉄棒が通されていた。
関東大震災を持ち堪えた免震造りの屋敷だった。
義父は義母を口説くときに災害に強い高台の屋敷もアピールしたという。
また水害にも神経質だったので義父の墓を高台に決めて(寺は義父の生家が決めた)ために墓参りは軽く登山。
私の父は義母と同い年だが住んでいた土地は関東大震災後に関東から越してきた人たちも多く、私が上京するときにとても心配していた。
なお、友人たちも東京は地震がくると心配していた。
災害用の備蓄は空襲と震災と伊勢湾台風に被災した母がうるさかったのである程度はしていた。が、夫は水は裏の墓地の井戸があるからという。
関東大震災後、焼けなかった山手のお屋敷でも胃腸の伝染病が流行ったときく、それは井戸水が汚染されたからだと軍歴ありの父談で、なので我が家には簡易浄水器(九八式衛生濾水機ではない)があった。
母も神経質だったので私も再婚するまでは簡易浄水器も置いていたが……
関東大震災を後世に伝えようと描かれた一群の作品が東京都慰霊堂に残る、中には今の学芸員さんが数年前に倉庫で再発掘したものもある。
修復されたそれらを観ることは大切だと私は思う。

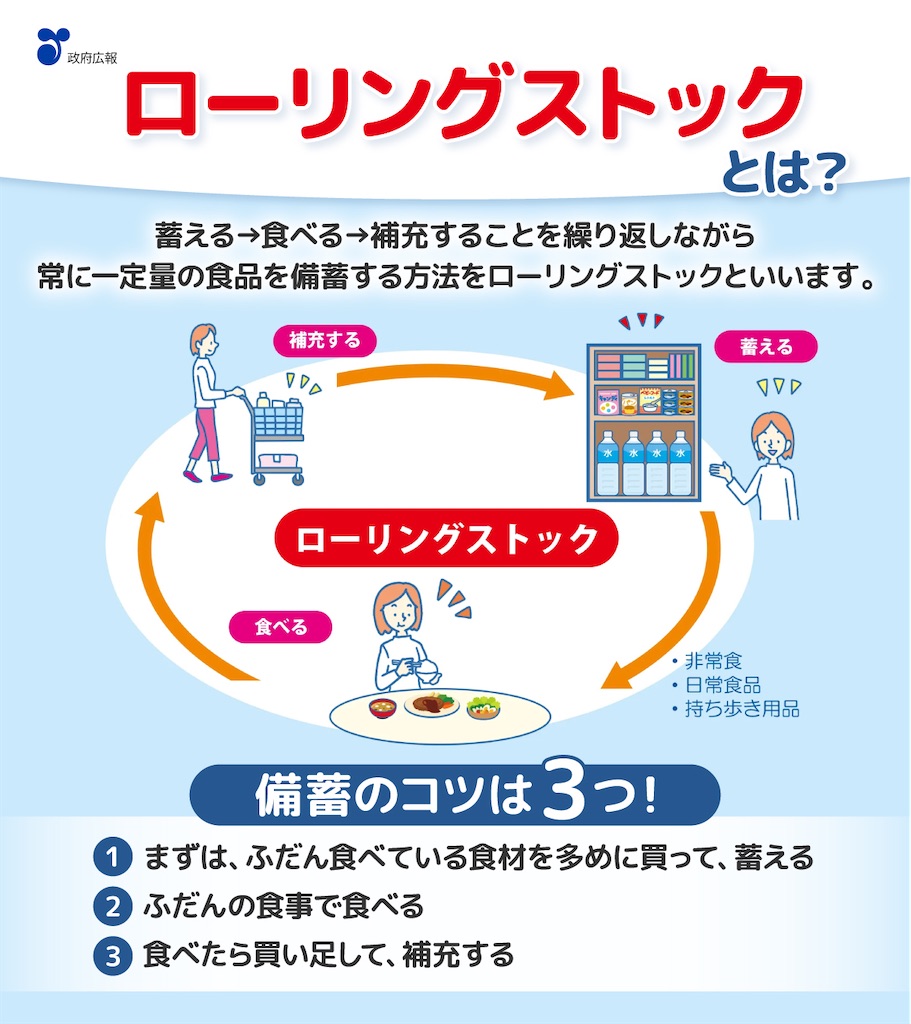
義父が尊敬していた中澤弘光画伯(お褒めいた手紙は表装して家宝になっている)の震災図は連作で、私は一作品を入手したが多分吉原の遊女たちの図。

中澤弘光画伯のこのシリーズ、他には江戸東京博物館が所蔵しているものもあり、中に流言、つまり噂話が広がる様を描いたものがあり、それも興味深い。
残念ながらどのような場で発表されたのかは調べ切れていない。
関東大震災図を描いて売り上げを寄付した画家もいたとかを読んだことがあるが、どの本で読んだかを忘れてしまった。ので、曖昧だ。
と、書いた後で以前の日記に残していたことに気がつき、一番下に再録しました。
たった2年前に読んだのにもう忘れてしまう。
去年の冬、白日会100周年の冊子に使う資料の撮影し直しに福島の村上鉄太郎画伯のご遺族宅に出かけ(押しかけ)、大正11年の浅草六区の写真などを複写した。その後震災で焼ける場所と被災する人たちの写真。
その作業中、中澤弘光画伯と伊藤清永画伯が並んで写生をしている写真が出てきて、ほぼ校了近くに出てきた写真が急遽冊子に収録された。
中澤弘光、村上鉄太郎、伊藤清永が存命だった時代を知る白日会会長の中山忠彦画伯がたいそう喜ばれて直に「ありがとう」と言っていただけたのが去年の春。
この秋に中山忠彦画伯の追悼展が熊谷伊助と熊谷登久平にも縁がある市川市で開催される。






以下再録
【震災・パンデミック · 2014/01/30 (たけいとしふみ 美術評論家/府中市美術館学芸員)】
関東大震災と美術―震災は美術史にどのような影響を与えたか
「日本近代美術の社会史」
2013年9月・10月、日本美術会附属美術研究所・民美で、「日本近代美術の社会史―震災と戦争から」
以下引用
「美術界への影響だが、まず展覧会の中止がある。秋口の土曜日であったので上野公園内の竹之台陳列館は、第10回を迎えた再興院展と二科展の招待日だった。作家たちが会場に集まってきた頃、地震が襲った。展示は即時中止で、秋の帝展も中止された。被災の実態だが、美術家の死者は少なかったといわれている。なぜなら、作家のアトリエは下町に少なく火災を免れたからである。他方、中心部に集中していた研究所・画廊・出版社等はほとんど全焼した。文化財の被害では、『大正震災志附録』に大倉集古館を含む164氏の所蔵家の損害が記載されており、失われた美術品は少なくない。
美術界の復旧は早く、救援活動も行われた。東京会場が中止となった院展と二科展は、地方展を実施する。院展は大阪と法政大学で、横山大観の全長40mに及ぶ山水絵巻《生々流転》などを展示した。二科展も、大阪、京都、福岡に巡回して大きな反響を呼ぶ。展覧会での収益は、被災会員の救援にも使われた。募金活動も行われ、後述する徳永仁臣(柳洲)ら東京青年画家同人会の「移動震災実況油絵展覧会」は、各地を巡回して義援金を集めた。また海外からの支援もあり、翌年11月には内務省社会局主催で「白耳義国作家寄贈絵画展覧会」が開かれ、皇族も購入して完売した。」